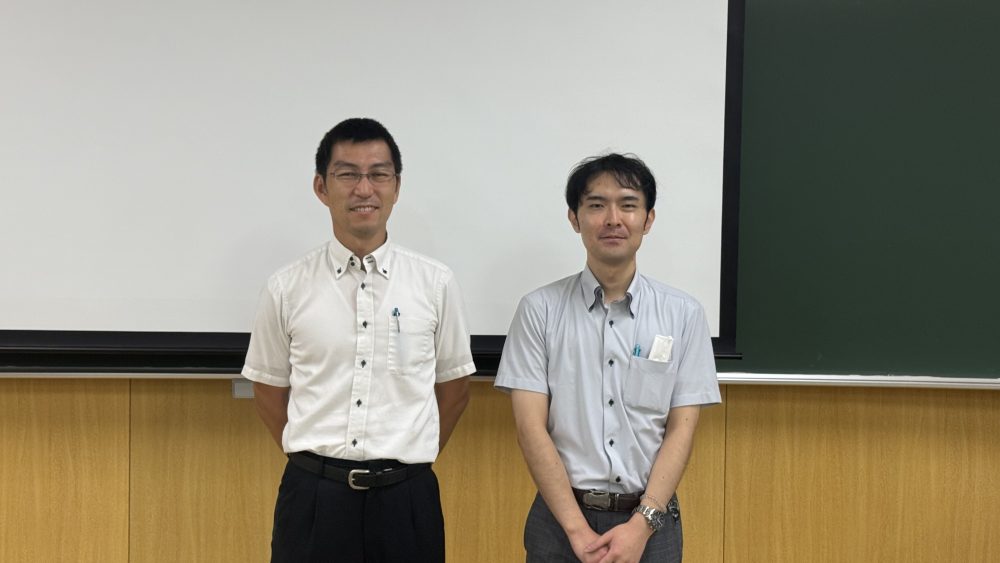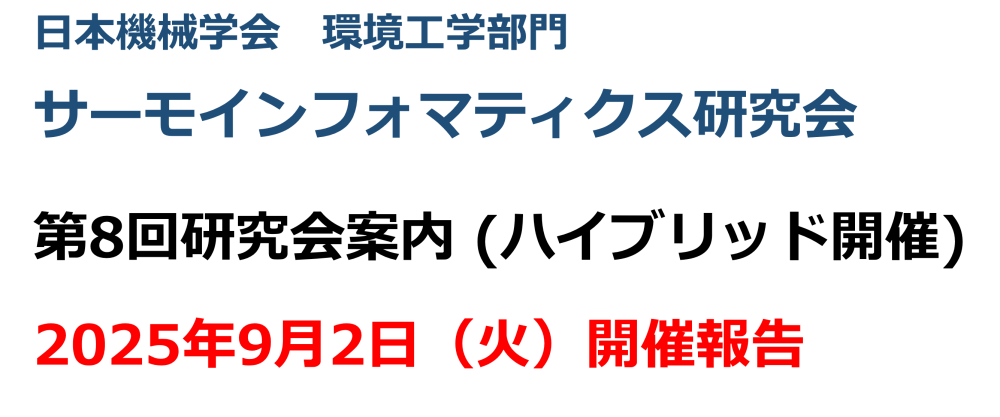第8回サーモインフォマティクス研究会開催報告
(文責:幹事 清)
2025年9月2日(火)10:00~12:00
第8回サーモインフォマティクス研究会を開催いたしました。今回はハイブリッドでの開催となり、参加者は36名(対面12名、オンライン24名)でした。参加いただきまして誠にありがとうございました。
発表1
「土木・防災分野におけるAI技術の活用」
日本工営株式会社の一言正之氏より、土木・防災分野におけるAI技術の活用について発表がありました。
一言氏は長年、洪水や土砂災害などのリスク評価やAI技術の実証業務に携わっています。
具体的なAIの活用事例は多岐にわたり、トンネルの画像評価やハンマー打音によるインフラ点検診断、気象モデルとAIを組み合わせた降雨予測などが挙げられました。未経験規模の洪水に対する予測精度向上のためのデータ拡張、AIの予測根拠を可視化するXAI(説明可能AI)、物理型モデルとAIを組み合わせたハイブリッドモデルによる高精度な予測も進められています。
深層強化学習を用いたAIによるダム操作は、仮想洪水を学習させることで下流への急激な放流リスクを低減できる可能性を示しており、人間の適切なルールや運用との組み合わせが重要だと強調されました。その他、画像生成モデル(GAN)による氾濫浸水予測等、多様な画像診断技術も紹介されました。
AI導入の課題としては、汎用AIと特化型AIの適切な使い分けが重要であり、土木・インフラ分野では特定の専門タスクに特化したAIが特に強力な影響を持つと指摘されました。AIの挙動から人間が学ぶ必要性も示唆されています。
発表2
「逆距離加重補間法に基づく流れと温度場の機械学習」
福岡県工業技術センターの大内崇史氏より、逆距離加重補間法に基づく流れと温度場の機械学習について発表がありました。これは電気通信大学榎木研究室での受託研究の一部をまとめたものです。
製品開発における熱流体解析(CAE)を活用した企業支援では、境界条件を変更した際の追加検討が頻繁に求められ、3次元空間での概算予測が必要となりますが、既存のメッシュ簡素化手法には限界があるため、機械学習を用いた予測が重要だと説明されました。
本研究の中心である逆距離加重補間法は、地学や気象分野で古くから使われてきた空間補間手法です。この手法は、未知の点の値を、周囲の測定点の情報を物理的な距離の逆数(重み付けの指数P=2を使用)で重み付けして予測します。解が陽的に求まり、暴走することなく安定して得られるという利点があり、測定点が対象の特徴を捉えていれば3次元的な補間も可能であると説明されました。
検証結果として、吹出温度が低く速度が速い条件では、IDWが温度分布や流線、職員体表面温度分布の熱流体解析結果の傾向を良好に再現できることが示されました。まとめとして、逆距離加重補間法は補間的な現象のみに対応可能で、外挿予測や、特に流れの構造そのものが変わるような条件の予測には不向きである可能性があるものの、必ず解が求まり、解が暴走せず、教師データが少ない状況での最適解探索の初動に有用な利点があることが議論されました。
今回の研究会では、AI技術の社会実装から熱流体解析における応用まで、幅広く実践的な知見が共有され、大変充実した内容となりました。
次回の研究会でも、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
講演資料については以下からダウンロードが可能です。(委員限定)